牧野富太郎が見つけたヤマトグサに「見つけた所」で出会う旅
はじめての方へ
First one
はじめての方へ

仁淀ブルーツアーについて
美しい仁淀ブルーの源流域にある仁淀川町は、四国山地の奥深い山国。
豊かな森の恵みと複雑な地層が生み出す、清らかな水や美しい森と山々の景観や、多種多様な植物が楽しめる、だけではないのです。
山国にかつて熱く息づいていた豊かな歴史と文化を、今伝えたい、消えないうちに。
この地で、昔の山里の、自然と暮らしと、懐かしいふるさとの味に浸ってほしい。そんなガイド付きツアーを紹介しています。
仁淀川はどんな川?
NHKスペシャルでその類まれなる美しい水が「仁淀ブルー」として放映されたことで全国に知られるようになりました。
5年連続水質日本一を誇る全長124㎞の仁淀川は、四国山地から流れ落ちる水を集めて太平洋に注いでいます。
その河口にある高知市内からは短時間で移動し、見て遊んで食べて学んで清流を楽しむことができる身近な川です。

Makino tour
牧野ツアーについて
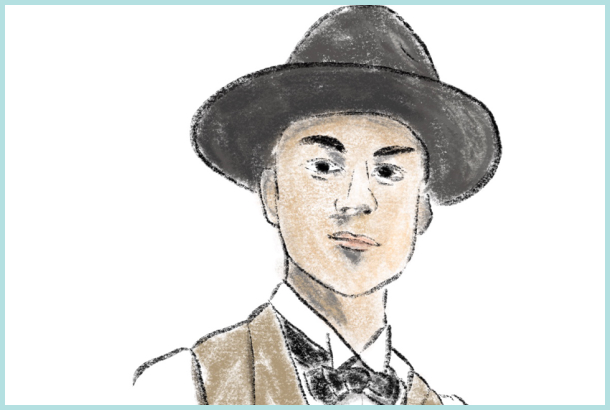
牧野富太郎はこんな人
牧野富太郎は、江戸時代末期(1864年)、
仁淀川流域の佐川町に生まれ、小学校も卒業せず、横倉山の自然に学び、
仁淀川町や県内各地から全国を歩いて新種を発見し、約1600種に命名をしました。
日本の植物学の基礎を築いた、日本の植物学の父と言われている学者です。
ヤマトグサとは?
明治17年(1884)、東大植物学教室に出入りを許されるようになった22歳の牧野富太郎が、上名野川でヤマトグサを発見しました。
ヤマトグサは、牧野富太郎にとって、その学名を、日本から世界に向けて発表するという日本人として初めての学問的業績の先駆けとなった植物です。


牧野をめぐる人々の関わりの舞台が名野川(仁淀川町)
名野川は、中津明神山1541mのふもとにあり、主に中津川流域の村々。
仁淀ブルーの豊かな森が、「生物多様性の宝庫」であることを、真っ先に気付いたのが、牧野富太郎です。仁淀川町に頻繁に通い、仁淀川町で採取された42種の新種に命名をしました。
しかし、名野川に来たことがない東大植物学教室の矢田部教授命名の植物も、2種ここで発見されています。
実は、この2人の確執に関わる舞台がここだったのです。
その詳細をぜひ牧野ツアーのガイドからお聞きください。

仁淀ブルー源流域の社寺を
巡るツアー

長州大工が建立したおよそ築200年の社寺
山奥の、人にほぼ出会わない森の中にある、大きくりっぱな社寺にびっくりします。素晴らしい彫り物がある、これらの神社や大師堂は、瀬戸内海を渡ってやってきた長州大工が、江戸時代末期から明治中期にかけて建築したものです。
なぜ彼らは、ここに来たのか。なぜ彼らは、このような建築物を建立したのか。
この地の人々と、彼らの盛衰と、残された社寺の物語は、昔の、山国の人々の歴史を象徴するようです。
もう200年近い年月の間、地元の方々が一生懸命守ってきました。しかし、山村の過疎は厳しく、守る人々は激減し、その維持管理は風前の灯火です。
ぜひ、今のうちに見に来てほしいのです。
Guide
ガイド・スタッフ紹介

メインガイド 杉本恵子
私は、仁淀川町の観光を考える会でガイドをしております。
仁淀ブルーツアーでは、必ず仁淀川町の観光を考える会のガイドがご案内いたします。
主に、仁淀ブルーで有名な安居渓谷・中津渓谷・にこ淵のガイドをしています。
美しい水を眺めて渓谷をご案内しながら、この地の自然や歴史や文化についてお伝えしています。
また、仁淀川町で多くの新種を発見した牧野富太郎とヤマトグサを紹介するツアーや、
長州大工の社寺を巡るツアーや、古くから伝えられてきた土佐清帳紙を紹介するツアーなどもご案内しています。
仁淀ブルーのアトラクションで遊び、ガイドツアーで学び、この地域の味を堪能していただきたいです。

